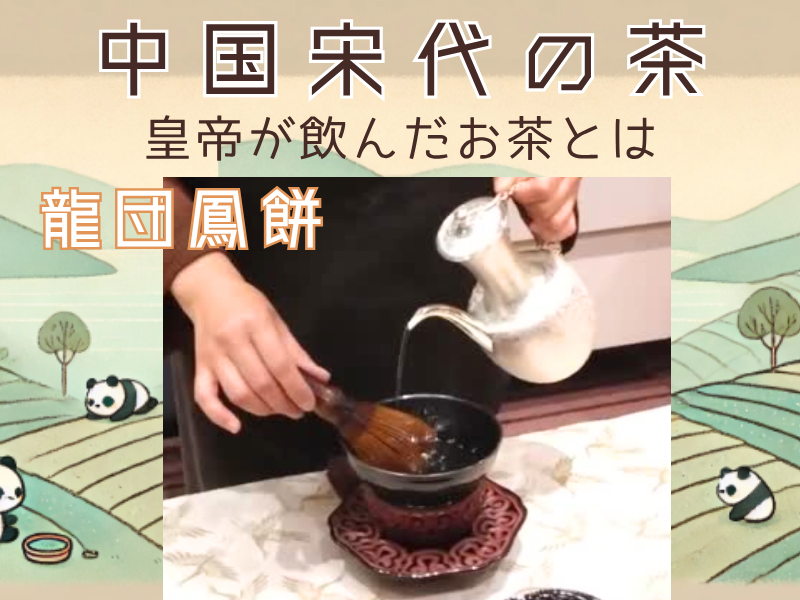中国宋代の茶の体験をしました。福建省の専門家が当時の道具、点て方だけでなくお茶の製法も再現したそうです。
目次
福建省から茶会のために来日
2025年5月、ドキュメンタリー『黄檗』の試写会があり、こ゚縁があり参加しました。
このドキュメンタリーは、福建省や黄檗山萬福寺が深く関わっており、黄檗宗の開祖・隠元禅師をはじめとする人々が日本にもたらした文化を主題としています。内容は、明朝体や茶をはじめとした六つのテーマに分かれて紹介され、日中の文化交流がその根底にあります。こうした背景から、会場は衆議院議員会館が選ばれ、国会議員の方々も招かれての開催となりました。お茶の専門家もこの日のために福建省から来日されました。
宋代茶文化の再現パフォーマンス
試写会に先立ち、中国福建省から来日された専門家による、中国・宋代の茶の再現パフォーマンスを拝見しました。日常の茶とは趣を異にした、宋代宮廷の茶文化を体感できるものでした。日本の煎茶道の茶会も催されました。
歴史的に有名な「龍団鳳餅」
宋代の中国宮廷では、「龍団鳳餅」と呼ばれる美しい固形茶を粉末にし、点てて飲む習慣がありました。現在のように茶葉を急須で淹れて飲むようになったのは、その後の明代以降とされています。

今回使用されていた龍団鳳餅は、原料・製法ともに当時のものに忠実に従って制作されたもので、年間にわずか15kgしか作られないそうです。その大部分は美術館に納められ、わずかに流通する分も非常に高価で、1餅あたりの価格を伺ったものの、あまりに桁違いで記憶から消えてしまいました。
粉にする工程も興味深く、通訳の方が見せてくださった動画では、茶臼ではなく杵のような道具で叩いて粉にしていました。
宮廷茶の味わい 泡をいただく?
私は天目茶碗でなく、中国茶用の小さな茶杯で少しだけいただきました。まず驚いたのは泡の存在感。まるで泡を食べているかのようで、その下にはとろりとしたわずかな茶(液体)がありました。泡は上質な苦味をもち、茶そのものは甘い・苦いといった言葉では表せず、ザラっとした(つぶつぶ感を感じる)質感と、軽さがありながら深みのある風味。
そしてふと一瞬、「野」のイメージが頭に浮かびました。はっきりと記憶はありませんが、自然を感じたのか、草のような感じだったのか…。淹れ手の方が、湯を少量入れて溶いていたときに薄い緑色でしたが、風味にも緑を感じるものがあったのです。

ただ、泡以外のものは茶杯を傾けてもなかなか口に入らず、ちゃんと味わえていたのかどうかというと…疑問が残ります。当時の人々は長い袖で口元を隠し、茶杯を舐めるようにしていただいたそうですが、現代の袖ではできませんでした。
固形の龍団鳳餅の形状や色から、プーアル茶のような熟成や深い味をイメージしそうですが、まったく違うものでした。
お茶の歴史では、宋の時代のお茶は泡の美しさを競ったとありましたが、日本の茶道の抹茶ような泡を想像していました。まさか、これほどの細かいきめでボリュームがあり、泡主体なものとは思いませんでした。
美しい宋代の茶道具
使用されていた茶道具も美しく、特に水差し(湯瓶)は優雅な形と質感で、目を奪われました。お茶碗は福建省建窯の建盞だそうです。泡が美しく引き立てられる黒色でした。

堆朱堆黒の天目台が使われているのを初めて目にしました。これまでは、単体で見ると個性が強く少し主張が強いとの印象を持っていましたが、実際にお茶碗を置き、茶席の雰囲気の中で見ると、不思議と自然に溶け込んでいて、妙に納得させられました。またこの天目台が、茶席全体に厚みや凄みを与えていたように感じます。動画の中でお茶碗を置いた様子を是非ご覧ください。

日を改めて、宋代の茶に関する絵画を見ていたところ、故宮博物院のサイトに『五百羅漢図』の紹介があり、宋代の茶道具についての説明を見つけました。天目台も見られ興味深くこちらにリンクします。
https://www.dpm.org.cn/subject_tea/single/detail/260798.html
引用:『五百羅漢図』は、南宋時代の僧により依頼され制作されたもの。その中の『備茶図』『吃茶図』には、風炉、炭ばさみ、茶磨、茶碾、茶末を入れる容器、湯瓶、茶筅、黒釉の茶碗、紅漆の盞托などの茶器が描かれており、南宋時代の寺院の点茶風景再現されてる。(大徳寺所蔵)
おわりに:ドキュメンタリー「黄檗」のご紹介予定
今回は、宋代茶文化の体験を中心にお届けしました。ドキュメンタリー『黄檗』の内容については以下をご参考ください。